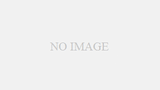観測史上最速の梅雨明けで、連日の猛暑に熱中症の救急搬送のニュースが騒ぐ中、なんだかモノ足りない気が・・・「あ!蝉鳴いてないやん!なんで?」と思ったのは私だけでしょうか?皆さんのところでは蝉鳴いてますか?コロン8の居住エリアは完全ではないですが割と自然豊かな土地なんです。朝は小鳥の鳴き声、この時期は蝉の鳴き声、秋は虫の鳴き声を感じることができる私史上最高のエリアなんです。それが、こんなに暑いのに蝉の鳴く声が聞こえないんですよね。「静かでいいけど・・・(本音)」なんでだろう?と思ったので調べてみました。
Z世代の皆様、楽しみの夏休みの自由研究のネタにお使いください。

暑さを耳からも感じるのは昔から蝉です。夏のBGMに蝉がいなかったことはありません。虫が苦手な私は、小学校の夏休み明けに蝉の抜け殻を大量に集めてくるクラスメートが結構な確率居ることが謎でした。中には「おじいちゃんが集めてくれた!」と嬉しそうに語る女の子も・・・「おじいちゃん、優しいね」としか答えられませんでしたが・・・とは言え、子供には大人気のセミさん。梅雨明けと同時に聞こえるはずの、「ジ〜〜〜ジ〜〜〜ッジ〜〜〜ジ〜〜〜ッ」みたいなのが聞こえてきません。
蝉の声は夏が進むにつれて暑苦しく盛り上げてきます。1週間ほどしか生きられない蝉。センターは順番に入れ替わります。
ニィニィゼミは夏の始まりに出現します。活動は6月後半から9月頃まで。生息域は北海道から沖縄(本土にはほとんどいない)まで日本を網羅しています。
体長は3cm〜4cm割と小ぶりです。歌詞「ジ〜〜〜ジ〜〜〜ッジ〜〜〜ジ〜〜〜ッ」
生息域は関東以西、九州、四国を中心に活動します。活動は7月に入り9月頃まで。体が大きいからクマです。6cm前後で丸々してます。
体が大きいので音量も大きいです。歌詞「シャンシャンシャンシャン」ひたすらシャンシャン・・・
クマゼミと同時期ですが、朝夕、少し涼しくなって鳴くのでクマゼミの次にしました。生息域は日本を網羅しています。大きさは4cmほどで、シュッとしています。
その鳴き声は美しくも不気味にも聞こえます。歌詞「カナカナカナカナカナカナカナ・・・」
夏のメインボーカルと言っても過言ではない、ミンミンゼミ、こちらも生息域はほぼ日本全土です。活動期間は7月から10月と長く体調も6cm前後ありますが、ボーカルらしくシュッとしてます。
歌詞「ミ〜ンミンミンミンミンミンミンミンミ〜〜〜〜〜〜ン」
こちらは沖縄にはほとんどいないそうです。北海道から九州までどこにでもいます。活動期間は7月から10月と長く、体長は6cm前後ですが、クマゼミよりスマート。鳴き声というよりも、リズム担当なので、3−2にしました。
歌詞「ジジジジジジジジージ、ジジジジジジジ」しつこい・・・
こちらも北は北海道、西は南西諸島まで生息しています。
活動期間は7月から長いところで11月に入っても生き残る個体がいます。体長は4、5cm前後、蝉の中でも容姿端麗です。立ち位置はコーラス部隊って感じですかね?歌詞「ツクツクボ〜シ ツクツクボ〜〜〜シッ」その歌は聞き手によっていろんな聞こえ方がします。
注※これを聞いて『西川のりお師匠』を思い出すことで、推定年齢と生息エリアがバレます。
早いものでは3月末ごろから鳴き出す種類もあるそうです。そのほか、沖縄のみに生息するセミや、指に乗せるような小さなものも・・・海外に生息するセミもいるようですが、四季がある日本では、夏の風物詩として愛されていますが、
海外ではあまり注目されていないようです。(完全に雑音扱いなのでしょうね)

蝉の羽化の条件を千葉県の小学4年生の児童がまとめたものが、千葉県教育研究会理科教育部会長賞を受賞しています。
1・気温が日中 30°C以上、湿度 80%以上で晴れの日が続くと抜け穴と抜け殻が多く見つかった。 2・地中温が 25°C以上になると、抜け穴や抜け殻の数が多く見つかった。
3・月の満ち欠けと抜け穴や抜け殻の数は関係がなかった。
『セミはいつ羽化するの』より
気温や地中温まで測り、月の満ち欠けに関する仮説も立て、素晴らしさを通り越して、学者レベルの小学4年生です。最後にリンクを貼っていますので、ぜひご覧になってください。と、、、気温も湿度もきっと地中温も条件的には当てはまっている気がしますが、雨が少なかったせいか、地中に水分が少ないのかもしれないな・・・ということで、私はサクッとネット内で調べてみることに。そもそもセミは卵から幼虫になるまでに1年かかるそうです。さらに幼虫になると地上に降りて土に潜ります。この地中で過ごす期間が驚きです。ツクツクボウシは1〜2年・アブラゼミは3〜4年・クマゼミは4〜5年潜っているそうです。そんな地中生活では、木の根から養分を摂取したり、モグラなどの外敵に襲われたりと意外と壮絶な人生を勝ち抜いた蝉が、老後の1週間を違う景色(夏の外の世界)を楽しむのです。短命だと思っていた、私たちが知ってる騒がしい蝉の姿は、晩年の姿なんですね・・・(これは知らなかったな・・・)
そう思えば、蝉の鳴き声の聞こえ方が変わってくる気がします。
(この記事は7月4日に作成しています)
紙谷准教授は「短い梅雨と少雨が影響している」と指摘する。土の中で育つセミの羽化には気温の上昇だけでなく、まとまった雨が不可欠。九州北部の梅雨明けの平年値は7月19日で、セミの活動が活発になるのも例年その時季だ。 ところが、今年は6月28日に異例の梅雨明け。期間も17日間と最も短く、雨量は各地で平年を下回り、半分以下の所も。紙谷准教授は「雨が少なく、タイミングを計りかねているのでは。今は『いつになったら降るのか』と待ちわびているのだろう」と見守る。
西日本新聞
観測史上最速の梅雨明けと共に、急激な気温上昇、6月の後半は熱中症も多発していましたね。私たち人間だけでなく、セミも困惑しているようです。地中での幼虫生活がメインだとすると、今年、羽化しなくても地中生活を生き延びる個体も多いのかもしれませんが、セミが鳴かない夏はなんだか不気味ですね。よく耳をすませば少しくらいはいるのかもしれません。台風4号が去ったあたりから一気に盛り上がって蝉のオーケストラが始まるのを待ってみます。
夏休みに知りたいことを思いっきり調べてみるのも楽しいですよ。泣きながら夏休み最後の2日間は宿題漬けだった私が言うなって?
いえ、今思えばもったいない時間の過ごし方をしたと反省しているからこそ言うんです!(笑)
参考・参照資料一覧
国土交通省 気象庁(https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html)
蝉の鳴く順番・ハルゼミから秋のチッチゼミまで
千葉県教育研究会理科教育部会長賞『セミはいつ羽化するの』←おすすめ
蝉の幼虫は土の中に何年いる?
西日本新聞『なぜ?梅雨明けても鳴かないセミ 押されていない「羽化スイッチ」』
error: Content is protected !!